

裏ワザ
ワイパーに雪が付着したら、窓を開けてワイパーが右側端に来た瞬間、右手でワイパーをつまみ上げて離すと、
ガラスにワイパーが当たり、衝撃で付着した雪が取れます。
ただし、注意力散漫になるので市街地の信号待ちなど、停車中に行ってください。
・ページのトップに戻る
・
雪道・ノウハウ・いろいろ 戻る
| ワイパーの拭き取り不良 | 車の後方、巻き上げた雪の付着 | オーバークール現象 | タイヤハウスの結氷 |
| 冬期間の運転・同乗者の健康 | 雪道・ブレーキのコツ | 気象情報の把握 | |
| ・ | |||
| ・ |
| ワイパーの拭き取り不良 |
| 雪が降ってワイパーかけると左の写真の様に氷が窓について視界不良になった経験ありませんか? これはフロントガラスが温まっているため雪が付着し拭き取れない現象で、ヒーターの温風がフロントガラス側 になっていると顕著に発生します。 ヒーター吹き出しは足元にするとガラスは冷えて雪は付着せず飛び去ります。 右側の様にワイパーは不用でクリやな視界が保てます。 ただし温暖時の降雪、市街地の低速走行や、初冬のベタベタ雪では逆効果です。 温風をガラス側にしましょう。 またファンの空気は「内気循環」にするとたちまち曇ります。 特に乗車人数が多いと吐く息の水分の逃げ場が無く、どんどん曇ります。 トンネルなど有害ガスの多い所以外は必ず「外気導入」にします。 |


| 車の後方、巻き上げた雪の付着 |
| 雪道を長時間走ると後方に巻き上げた雪が貼り付き、テールランプ・ストップランプも後方車に届かず、 追突される恐れがあります。常にスモールランプを付けて走ると、ランプハウスの温もりで雪が融け、ランプ点灯の 確認ができます。見通しの良い雪道でも、巻き上げる雪がある所では、スモールランプを点けて走りましょう。 但し、最近のLEDランプ使用車は発熱しないため、点灯してもランプハウスが暖まらず、 雪が下の写真の様に雪が融けません。右は発熱灯ランプ車で、かろうじて点灯が分かります。 |


| オーバークール現象 |
|
 |
−15℃程度になると、エンジン温度が上がらず、ヒーターも効かなく なることがあります。「オーバークール現象」と言います。 ラジエターの前面をダンボールなどで1/3〜1/2(半分)程度 覆うと 解決します。 冬期間、私の車はダンボールで半分覆ったままですが、オーバーヒート やその兆候など一度もありません。春になったら取り外してください。 最近の車はファンの制御まで自動化しているので「オーバークール」は 少ないか、無いと思います。 ← ラジエターの左半分をダンボールで覆った、26万キロ走破の旧 マイカー。今乗ってるエス・ハイは何もしなくてもOK |
| タイヤハウスの結氷 |
|
 |
−5〜0℃程度の冬道を走ると、左のようにタイヤハウスが結氷してき ます。このまま放っておくと、ハンドルが切れなくなったりします。 走行中に少しの揺れで『ウィーン』と言う、うなり音が発生し始めたら タイヤハウスの氷にタイヤが当たる音です。 私の経験では2時間以上の走行で氷が厚くなってくるようです。 音がし始めたら・・・また、停車したときなど、氷を靴でけ飛ばして 落とします。 氷を落とすのは、なるべく駐車帯で行い、走行車線上に氷を落と さないように気を付けましょう。(石と同様なので危険です) タイヤが当たる部分の氷を落とすだけでOKです。あまり神経質に たたき落とすと、車が傷みます。 |
| 冬期間の運転・同乗者の健康 |
| 冬期間、ヒーターを使う狭い車内は10〜30%以下に異常乾燥しています。長時間車内に閉じこもった運転手・同乗者はノドを傷め、 目は雪の紫外線で傷み、ドライアイ化し、更に長時間の車内閉じこもりは「エコノミークラス症候群」⇒ 「静脈血栓塞栓症」も引き 起こす、極めて健康に悪い状態と思いましょう。 少なくとも「2時間運転したら休息をとる」のが基本です。北海道の「道の駅」はH27年2月現在115ヶ所登録されています。 ここは広い駐車場・飲料設備・24時間トイレ・地域の情報・特産品の販売など、単なる休息施設ではない地域と密着した 機能があります。ぜひ立寄って休息し、地域の情報収集もして見ましょう。 ・ |
| 雪道・ブレーキのコツ |
| 冬道ブレーキのコツは「新幹線ブレーキ」です。新幹線は停車ポイントに達する前に充分減速し、ゆっくり停車ポイント近づいて 停車します。この方法を身に付けると、滑ったり滑らなかったり多様な路面状況でも、いつも安定に確実に停車する 事ができます。後続車の追突も避けられます。「ポンピングブレーキ」や「エンジンブレーキ」は仮目標への減速時に 使うテクニックとして使いましょう。 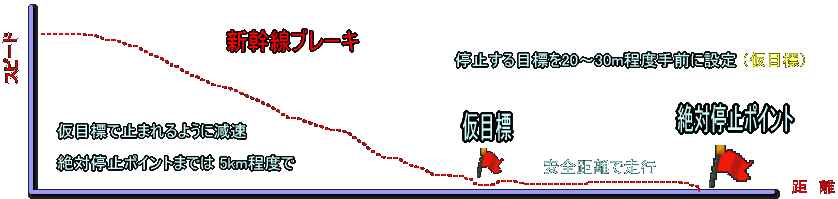 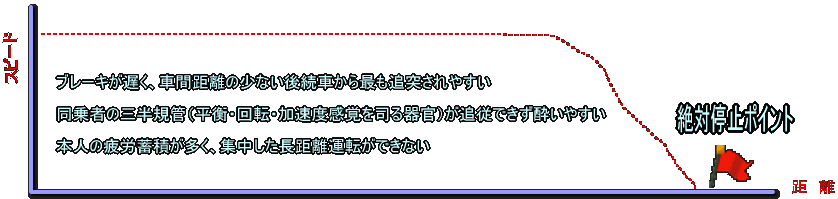 新幹線に乗る機会があったら「究極の新幹線ブレーキ」を観察して見てください。 ★ 市街地の下り坂は平坦路の何倍もの制動距離が必要で、エンジンブレーキでゆっくり降りて行かないと、 事故遭遇の確率が上がります。一般に「函館」など坂道の多い都市では「登り・下り側を優先」とし、幅広い平坦路側 を「一時停止」にしています。普通の町では幅広い方が優先で、狭い道が夏冬通して「一時停止」です。 ・ |
| 気象情報の把握 |
| 北海道の冬は気象の変化が激しいため、遠出する場合は必ず気象の確認をするのが普通です。 また標高の高い峠が多く、平地は平常でも峠は荒れている事は普通に多いです。 R273号・三国峠(1,139m), R39号・石北峠(1,050m),R274号・日勝峠(1,022m),R230号・中山峠(835m) 北海道の標高1000mは緯度が北のため、本州の3000mと同様の気候・温度です。 カーラジオはほぼ1時間毎に峠や道路の情報を流しています。 冬の道は常に情報収集をして「荒れる予報」 の場合、北海道の一般ドライバーは「峠の通過を止める」のが普通です。 北海道は土地が広いので夜間 AMラジオのローカル放送を見つけるのが困難です。 (中波の伝播が良くなり他局の電波が混信するため) 「携帯電話」や最寄の「道の駅」・「道路情報板」に頼るのが良いようです。 私のように夜間走行やお客様を乗せた走行では、スマホを使っての情報収集が欠かせません。 |
| ページのトップに戻る |
・