 ・ |
| カタバミ (片喰・傍食) 【カタバミ科】 「多年草」 花時期: 6~9月 長さ:30~50cm 程度 | 戻る |
| 分布: 北海道・本州・四国・九州 生育場所:道端・空き地・畑 など 学名:Oxalis corniculata L. | |
 ・ |
| ◆ 畑では雑草として嫌われることが多い。 草取りでは種子ができるまでに早めに取り除くことが、繁殖防止になる。 |
| ◆ 花時期が長く、種子がはじけて拡散し、アチコチで芽を出して繁殖すると共に、茎は匍匐枝を出し地面を這い、所々で根を出して広がっていく。 |
| ◆ 葉には蓚酸(しゅうさん)が含まれていて鏡を磨くのに使える。 虫に刺された時、この葉をもんで塗布すると効き目がある。 |
| ◆ 発芽すると真下に太目の根を伸ばし、今度は枝を横に伸ばして広がって行く。 種がはじけて飛び散ると、手に負えないほど増えて行く。 |
| ◆ 夜になると葉を閉じて寝る(就眠運動)。 葉の一部が食べられたように見えるのでカタバミ(片喰・傍食)と和名の由来になっている。 |
| 「カタバミ」の特技? |
| カタバミの種子にはゼリー状の粘液が附着している。 アリの好むエライオソームであろうと言われているが、これは成熟した蒴果に動物が触れると、 |
| 種子が勢いよく弾き飛ばされ、その動物に附着して拡散する接着の役目ではないか・・と思われる。 |
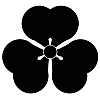 |
← この「カタバミ家紋」は、美しい葉の形と繁殖力の旺盛な「カタバミ」を例え「子孫繁栄」などの 意味する家紋として多くの武家で愛用された。 左の紋を基本として、たくさんの「カタバミ家紋」が愛用されている。 |
| 戻る | 索引TOPへ |